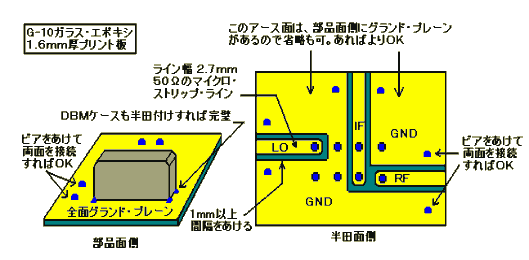DBMの使い方をマスターしよう!
DBMは非常に特性がよく、広い適用範囲をもつミキサーであり、DBMは局発のレベルや、入出力インピーダンスをマッチさせさえすれば、ミキサーのすべてをDBMに置き換えることができるといえるほどです。ぜひDBMの使い方をマスターしましょう!
 必要とする目的によって、DBMの各端子を入れ替えて使おう。
必要とする目的によって、DBMの各端子を入れ替えて使おう。
DBMには、概略構造図で示したようにRF,LO,IFの3端子があります。通常の使い方としては、RFが入力信号(小さな信号)、LOが局部発振器信号(大きな信号)で、IFが出力端子になります。
ここで動作原理を、もう一度思い出してください。3端子をそれぞれ入れ換えた場合でも、それぞれ動作するということで、RF,LO,IFの3端子は厳密には決められているわけではありません。必要とする目的や性能によって、おのおの入れ換えてもかまわないのです。
まずIF端子ですが、表1で見るように、ほとんどのDBMはIF出力がDCから可能になっています。他の端子は、ほとんどDCは扱えませんので、IF出力としてDCあるいはごく低い周波数が必要なときのみ、IF端子が有効になります。
スペアナの簡易バージョンのブロック図で、UPコンバーターがあります。ここで、入力信号端子にIF端子を選びましょう。IF端子を選べば、スペアナの測定範囲をDCまで拡張できます。
現在、秋月電子通商で扱っているDBMモジュール(ミニサーキット社製)には、表1の3種類あります。SBL−1は、値段が一番安いのですが、入力周波数範囲は500MHzまでとなっています。TUF−5は、値段が結構しますが、LO/RF入力周波数範囲が1500MHzまで使えます。変換損失、アイソレーション特性については、表記の入力周波数範囲内では、目立った違いがありません。
私は、値段が手頃であるTUF−2を一番よく使います。
表1. 秋月電子通商のDBMモジュールについて
| 種類 |
LO/RF
入力周波数 |
IF入力周波数 |
変換損失 |
LO−RF
アイソレーション |
値段 |
| SBL−1 |
1〜500MHz |
DC〜500MHz |
8.0dBmax |
45dBtyp |
750円 |
| TUF−2 |
50〜1000MHz |
DC〜1000MHz |
9.0dBmax |
47dBtyp |
900円 |
| TUF−5 |
20〜1500MHz |
DC〜1000MHz |
9.0dBmax |
42dBtyp |
1,500円 |
 局部発振器のパワーがある程度あれば、変換ロスは一定
局部発振器のパワーがある程度あれば、変換ロスは一定
図6に、局部発振器のLOレベルに対する変換ロスの変化を示します。このグラフで注目すべきことは、変換ロスは局発(LO)のレベルが、約+6dBm〜+14dBmの間で、ほぼ一定の約6dBであることです。
すなわち、発振器のレベルがこの間で変動しても、変換ロスが一定であるため、発振器の出力を一定にする努力をはらわなくても良いというのが、DBMの魅力の一つです。アクティブなミキサーICでは、変換ロスを考慮する必要はありませんが、だからといってDBMが劣っているというわけではありません。変換ロスが一定と分かっているため、後段の増幅器などで損失分を補償すればよいのです。
ただし、LOレベルのパワー不足は具合が悪く、約+3dBm以下では変換ロスが大きく変動してしまいますので注意する必要があります
前ページのDBMの動作原理を考えると、このLOパワーによってダイオードのスイッチングをONさせるわけで、大きな信号とは定量的に言えば、+3dBm以上ということになります。
 |
図6. LOレベルによる変換ロスの変化
|
DBM:TUF−2使用
条件: LO周波数 500.0MHz,LOレベル0〜+14dBm
RF周波数 470.0MHz,RFレベル−10dBm
IF周波数 30.0MHzのIF出力レベルより測定 |
 RF入力信号は、十分に小さく
RF入力信号は、十分に小さく
DBMの局発信号LOは、ダイオード・スイッチをON/OFFさせるので、これに十分なパワー(約+3dBm以上)が必要であると述べてきました。一方、RF入力信号は、LO信号によるスイッチングのタイミングを乱さないよう、LO信号よりも十分にレベルが低い必要があります。目安として、−10dBm以下であることが無難でしょう。
図7にDBMの入出力レベル特性を示します。入力レベルが−40dBm〜−5dBm程度までの範囲で、出力レベルはー46dBm〜−11dBmとなり、概ね直線性を保っています。出力レベルと入力レベルの差が、ちょうど変換ロスとなっており、6dB程度であることが分かります。
入力レベルが大きく0dBmを越えたあたりから、特性の曲がりが見え始めています。この曲がり始めた領域以上でDBMを使ってはいけません。ダイオード個々にとっては、LO信号とRF信号の違いは、ダイオードをONできるか否かのレベルの違いだけなので、LO信号は大きく、RF信号は小さく、というのがDBMの動作上守るべき基本的なルールだと思います。
−40dB以下の特性については、レベルが小さいためか測定上の都合で測定できませんでしたが、−100dBm以下まで十分直線性を持っていると言われています。使用信号の下限は雑音レベルで決まるため、そのダイナミック・レンジは100dB以上と推測されます。この理由は、DBMのダイオードがスイッチング動作をしていてON抵抗も小さいので、それ自体はほとんど雑音を出すことがないからです。アクティブなミキサーICと比較して、雑音レベルにおいても優れています。
 |
図7.入出力レベル特性
|
DBM:TUF−2
条件: LO周波数 500.0MHz,LOレベル+10dBm
RF周波数 470.0MHz,RF入力レベル−40〜+5dBm
IF周波数 30.0MHzのIF出力レベルを測定 |
 DBMの各端子は50Ωと規定されているわけではなく、75Ωでも使用できます。
DBMの各端子は50Ωと規定されているわけではなく、75Ωでも使用できます。
前ページのDBM動作原理図の内部構成から考えて、DBMが50Ωのインピーダンスに規定されている要素は察せられません。特性は50Ωで測定され、50Ωに良いよう素子が決められているにすぎないのです。そのため、特性は若干低下しますが、75Ωでも使用できます。特性の変化は微々たるもので、気にするほどではありません。
したがって、Giga-Siteスペアナの各ユニット構成は75Ω系なので、DBMを使ったUP/DOWNコンバーター・ユニットに置き換えた場合でも、まったく問題ないと考えられます。
 LO信号は、正弦波でなくてもかまいません。
LO信号は、正弦波でなくてもかまいません。
DBMの局発信号LOは、ダイオード・スイッチをON/OFFさせるのが目的です。正弦波よりむしろ方形波の方が適しているとまで言われています。すなわち、LO信号が正弦波であると、ダイオードが全てOFFとなる時間があるためです。従って、方形波で駆動すればOFFとなる時間が短くなるため、それだけ変換ロスは少なくなります。
 後続のフィルターの特性が甘いものですむ。
後続のフィルターの特性が甘いものですむ。
DBMはアイソレーションをもっており、局発信号の漏れが少ないため、アイソレーションのないミキサーを用いた場合に比べて、後続のフィルターの特性が甘いものですむという利点があります。
 DBMのピン配置について
DBMのピン配置について
それでは、DBMのピン配置について説明します。図8にDBMの構造と対応するピン名称を示します。図9,図10は、それぞれTUF−2,SBL−1の外観及びピン配置図です。BOTTOM VIEWを見ると、ピンの足の付け根に色が付いています。青色が1ピンになります。TUF−5は、TUF−2と同じピン配置です。
TUF−2(TUF−5)のピン配置(図9.BOTTOM VIEWの左側が1ピン)
1ピン: RFポート(青色)
2ピン: IFポート(緑色)
3ピン: GNDポート(無色)
4ピン: LOポート(緑色)
SBL−1のピン配置(図10.BOTTOM VIEWの右下が1ピン,左上が8ピン)
1ピン: RFポート(青色)
2ピン: GNDポート
3ピン: IFポート
4ピン: IFポート
5ピン: GNDポート
6ピン: GNDポート
7ピン: GNDポート
8ピン: LOポート
 |
| 図8. DBMの構造図 |
 |
| 図9. TUF−2のピン配置図(TUF−5も同じ) |
 |
| 図10. SBL−1のピン配置図 |
 基板へ実装の仕方
基板へ実装の仕方
DBMのピン配置が分かったところで、DBMを基板へ実装の仕方を説明します。以前に「特集 秋月のキットを完璧に作る」、と題したもので、500MHzまでのスペアナの作製記事/CQ誌(CQ HamRadio 1997.11月号 p.126参照)で掲載されていた方法は、モジュールの上端側(TOP VIEW)を直接基板へ半田付けするということで紹介されていました。
DBMやVCOのパッケージ上面は、内部回路に直接接しておらず、モジュールはピンに近いところに位置していることから、ピンを直接半田付けするのは熱ストレスが加わるためという理由でした。DBM、VCOとのピン間の回路結線は、空中配線で行っているようです。
でも、ちょっと待ってください。私の経験の範囲では、ピン側を半田付けして特に問題が生じたことはありません。むしろ、パッケージ側を半田付けするときに、熱容量の小さな半田ゴテを使用した場合、パッケージに半田が付く温度に達するのに時間がかかって、かえって肝心のモジュールを壊すのでは?と心配します。
さらに実は、私は、ここで扱うDBM,VCOは高周波部品として1GHz以上までも使用するため、プリント基板への実装は重要であると考えております。DBMの各端子は50Ωに規定されていないから、リード線で短くつなげさえすればよいという意見もありますが、同じ部品を使っても基板への実装の仕方でノイズに弱くなったり、期待通りの特性が得られなかったりするのです。
プリント基板は、せめて両面板を有効に使い、信号ラインを50Ωのマイクロ・ストリップ・ラインにして、伝送ラインとするべきところなのです。
マイクロ・ストリップ・ラインとは、何ぞや?、と初めて聞く方もいるかと思います。マイクロ・ストリップ・ラインの原理・作り方の詳細は、今後連載で説明しますが、そんなに難しいものではありません。
図11のような幅のラインを引いたプリント板を作ればよいのです。部品面側は、グランドプレーン(全面銅箔)とし、半田面側に一定の幅をもたせた信号ラインを引くことです。
プリント板のエッチングなどが苦手な人もいるかもしれません。そんな場合でも、ユニバーサル基板(たくさん穴が開いている万能基板とも呼ばれるもの)を利用することが出来ます。ただし、材質はガラス・エポキシのものを使ってください。ベーク板は安価なのですが、高周波特性はあまりよくありません。
次に銅箔シールを用意します。部品面側には、銅箔シールをDBMの周囲全面に張り付けてください。半田面側には、一定の幅に切った銅箔ラインを張り付ければ、簡易的マイクロ・ストリップ・ライン実装基板の完成です。実装の推奨は、やはりプリント基板をエッチングして、マイクロストリップラインを形成したものです。プリント基板の作製方法についても、今後掲載していく予定です。
ラインを曲げるときの形状は、どうしたら良いかとか、その辺のレイアウトのノウハウについても、今後掲載していきたいと思っています。ここでは、DBMの実装付近について示しておきます。
図11には、ケースの四隅に半田付けする例が書かれておりますが、60W〜100W程度の比較的容量の大きな半田ゴテを使用し、短時間で半田付けした方が、きれいに仕上がって外観も良くなると思います。
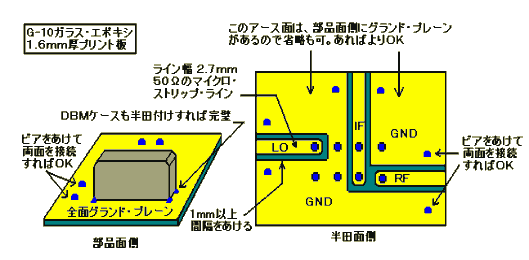 |
| 図11.DBMの基板実装図 |
[次へ]は、VCOの使い方をマスターしましょう。